- web広告の不快感に悩んでいる
- 自社広告がユーザーに悪印象を与えていないか気になる
- 不安や煽り系のクリエイティブに頼らず効果を高めたい
- ユーザーの心理を理解した広告設計を学びたい
こんにちは、「株式会社DXマーケティング」です。
「あのweb広告、なんだか気持ち悪い…」そんなふうに感じる経験をしたことはありませんか。
日々インターネットを利用していると、個人的な情報を深く追いかけてくる広告や、刺激の強いビジュアルが急に表示されると、不快感を覚えることも少なくありません。
一方で、企業がweb広告を運用する立場から見ても、「もしかして自社の広告がユーザーを不安にさせていないか」「気持ち悪いと思われてしまっていないか」と心配になるケースもあるでしょう。
ユーザーに不快感を与える広告は、ブランドイメージを損ねるだけでなく、売上やリピート率に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで本記事では、どうしてweb広告が気持ち悪いと感じられてしまうのか、その回避策や効果的な設定方法、さらにユーザーの心理を踏まえた広告設計のポイントを詳しく解説します。
また、「株式会社DXマーケティング」が提供しているWEBマーケティング全般やLP制作、LINE構築、広告運用といったサービスを活用することで、ユーザーに安心感を与える広告づくりをどう実現できるのかについてもご紹介します。
「なんだか気持ち悪い…」という印象を与えないためには、単純に広告をブロックするだけでなく、広告を提供する側の企業がどう考え、どう設計するかも非常に大切なポイント。
この記事を読むことで、不快感の少ない広告運用と、ユーザーの心理を理解したクリエイティブの在り方がきっと見えてくるはずです。
web広告が気持ち悪いと感じる理由

web広告を見たユーザーが「気持ち悪い…」と感じる理由には、さまざまな要素が関係しています。
とくに、ターゲティングの過剰さや、過激な表現を使う広告が増えると、ユーザーは自身のプライバシーが侵害されている感覚や、恐怖心を抱くケースがあります。
一方で、広告主の企業側は、「できるだけ効果を高めたい」「ユーザーの興味を引きたい」という意図から、つい踏み込みすぎた手法を選択してしまいがちです。
しかし、その結果がブランドイメージの低下やユーザー離れを引き起こすのであれば、本末転倒といえるでしょう。
ここでは、web広告が気持ち悪いと感じられる主な要因を3つ取り上げ、詳しく解説していきます。
これらの要因を把握することで、企業として広告を出稿する際に注意すべきポイントが見えてくるはずです。
個人情報に踏み込みすぎるターゲティングの問題
- ユーザーの検索履歴を追跡するリターゲティング広告
ユーザーが特定の商品やサービスを検索した直後、さまざまなサイトでその広告が追いかけてくる現象を目にしたことがあるでしょう。これはクッキー(Cookie)や閲覧履歴を活用したリターゲティング手法です。
便利な反面、「そこまで監視されているのか」と恐怖感や気持ち悪さを覚える方も多く、個人情報保護の観点から批判されることがあります。 - 過度に細分化された興味関心ターゲティング
広告主としては、購買意欲の高いユーザーにピンポイントでアプローチしたいあまり、年齢、性別、職業、趣味嗜好などの多角的なデータを用いて配信するケースがあります。
ただ、ユーザーが「なぜこんな自分しか知らないような趣味を知っているのか」と感じるほど細かく表示されると、不気味さを感じてしまうのです。 - プライバシーポリシーの不透明さ
サイトやアプリのプライバシーポリシーが曖昧なまま、個人情報を活用しているとユーザーの不信感が高まります。適切な説明や同意プロセスなしにデータを収集・利用されると、「勝手にデータを使われている」という印象を強く与えてしまうでしょう。
これらの過剰ターゲティングは、確かに広告効果を高める側面がある一方で、ユーザー体験を損ねる危険性も併せ持ちます。
広告設計時には、「どこまでが適切な範囲か」を考慮し、プライバシーに配慮した設定を行うことが重要と言えます。
過激なビジュアルや表現のインパクト
- ショッキングな画像やグロテスク表現
広告の目に留まるインパクトを狙い、過度に刺激的な画像を用いる場合があります。しかし、人によっては不快感や嫌悪感を抱くほどの強烈なビジュアルが繰り返し表示されると、気持ち悪いと感じるユーザーが増える恐れがあります。 - 誇張表現や嘘に近いキャッチコピー
商品やサービスの効果を大きく見せるために、誇大広告とも取れる表現を使うと、ユーザーに対する裏切り感が生まれます。結果として「騙されているかも」という不信を抱き、不快感へとつながることも多いのです。 - 性的・暴力的要素の強い広告
一般的には年齢制限を設けるなど配慮されるべき領域でも、配信先の設定や審査の甘さにより、不特定多数が目にする場に出てしまうケースがあります。社会的・倫理的に配慮が欠ける広告は、批判が高まりやすく、企業イメージを著しく損なうリスクがあります。
広告のクリエイティブは、ユーザーの「見たい」「もっと知りたい」という積極的な気持ちを引き出す表現が理想です。
しかし、過激さだけを追求すると、かえってブランドや商品そのものに対する悪印象を残してしまうため注意が必要と言えます。
ネガティブ感情を煽る不安商法的な訴求
- 「このままだと危険」「今すぐ何とかしないと手遅れになる」
など、強烈な不安を煽るコピーは一瞬のクリックを誘導するかもしれませんが、ユーザーにとっては嫌な印象が残りやすい手法です。 - 「あなたにだけ特別」
といった文言が乱用されると、真実味が薄れ、「怪しい広告だ」と疑念を持たれやすくなります。 - 脅しのようなセールス手法
たとえば健康商品や美容商材で、「〇〇をしないと将来××になりますよ」といった恐怖心を過度に利用する手法は、ユーザーの自主的な判断を阻害し、ストレスや不快感を増幅させる原因になります。
ネガティブ感情を刺激する広告は、短期的に注目度が高まるケースがある一方で、長期的にはブランドへの好感度を下げるリスクが大きいと考えられます。
ユーザーとの信頼関係を重視する企業ほど、こうした訴求手法は避けたいところでしょう。
不快なweb広告を回避するために知っておきたい設定やツール
ここまで、web広告が気持ち悪いと感じる原因を解説してきました。
しかし、利用者側からすると「広告をまったく見たくない」と思うケースもあるでしょう。
そこで、ユーザーが不快な広告を少しでも減らすために活用できる設定やツールについて、概略を押さえておくと便利です。
もちろん、企業として広告を出す立場であっても、「ユーザーがこれだけ対策を講じるほど、広告に不快感を覚えている」という実情を知ることは重要と言えます。
以下の3つの小見出しでは、ブラウザ設定や広告ブロッカー、スマートフォンでの対策などを紹介します。
最終的には広告主とユーザーが互いに快適な環境をつくるためのヒントとして考えてみてください。
ブラウザ設定と広告ブロック拡張機能
- ChromeやFirefoxなど主要ブラウザのプライバシー設定
ユーザーが自分でクッキーの使用を制限したり、追跡防止機能を有効にすることで、リターゲティング広告をある程度減らすことができます。 - 広告ブロッカー拡張機能(AdBlock, uBlock Originなど)
無料で使えるものが多く、ある程度の広告を除去するには有効。ただし、ウェブサイトによっては広告ブロッカーを検出して利用を制限したり、広告ブロックをオフにしないとコンテンツが閲覧できないケースもあるため注意が必要です。 - 追跡型広告のオプトアウト
一部広告配信事業者は、ユーザーが興味関心に基づいた広告の配信を停止(オプトアウト)できる仕組みを提供しています。ブラウザの「広告設定」や「プライバシー設定」を確認し、不要であればオプトアウトする選択肢もあります。
これらを組み合わせることで、過度に気持ち悪いと感じる広告が出にくくなる場合があります。
ただし、広告ブロックの徹底は、サイト運営者の収益モデルを損なう懸念もあるため、ユーザーとしては使い方に慎重になる必要があります。
広告配信プラットフォームのカスタマイズ活用
- Google広告の「広告設定」
Googleアカウントにログインしている場合、「広告設定」で興味関心のカテゴリをカスタマイズできます。不要なカテゴリをオフにすると、ある程度「的外れな広告」や「不気味なほど詳細に狙われた広告」の表示を減らすことが可能です。 - Meta広告(FacebookやInstagram)の広告優先度調整
アプリ内で広告のフィードバックを送ると、興味のない広告が減る仕組みがあります。逆に、興味のある広告には「興味あり」のリアクションをすると、より自分に合った広告が流れるようになることも。 - YouTubeのスキップオプションや広告制限
スキップ可能広告や広告の長さに関して、ユーザーがオプションを変更できる場合があります。特に、過激な動画広告を目にする回数を減らしたい人には有効です。
広告の受け取り方をユーザー自身がコントロールできるというのは、近年の広告プラットフォームが意識している流れでもあります。
企業としては、こうしたユーザーの行動を踏まえて、より「わかりやすく」「無理のない」広告配信を心がけることが大切でしょう。
スマートフォンでの対策と注意点
- iPhoneの「Ad Tracking制限」
Apple製端末では、ユーザーが設定で「広告トラッキングを制限」をオンにすることで、アプリ間でのデータ利用を大幅に制限できます。 - Android向け広告ブロッカーやアプリ制限
Google Playで配布されている広告ブロックアプリをインストールするなど、ある程度対処できますが、端末やOSのバージョンによって使い勝手が異なる場合があります。 - 広告を表示しないアプリ利用のリスク
無料アプリの多くは広告収入を主な収益源としています。広告ブロックやオフライン閲覧などを多用すると、サービス提供者への正当な対価が不足し、サービスが存続できなくなる可能性もあるでしょう。
スマートフォン利用が急増している現代において、ユーザーが不快な広告を敬遠する行動を取るのは当然の流れと言えます。
そのため企業は、「ただブロックされるのではなく、自社の広告を見たいと思ってもらうにはどうすればいいか」という視点で広告設計に取り組む必要があるでしょう。
web広告を「気持ち悪い」と思わせないための設計ポイント
ここからは、広告を出稿する側の視点で、「気持ち悪い」と思われないための具体的な設計ポイントについて掘り下げます。
どんなに広告が高性能・高機能化していても、ユーザーに不安や嫌悪感を植え付けてしまっては、最終的には企業の損失につながってしまうはずです。
「ユーザーに寄り添った配慮」「ポジティブで建設的な体験の提供」が重要ですが、それを実現するには広告のクリエイティブやデータ活用の考え方を大きく見直す必要があるでしょう。
以下の3つの小見出しを押さえることで、長期的に信頼されるブランド作りにつなげる方法を確認してみてください。
ユーザーのプライバシーを尊重するデータ活用
- Cookie使用やデータ収集の明確な説明
広告主のウェブサイトやアプリが、Cookieや行動履歴をどのように利用するかを、事前にわかりやすく提示するとユーザーの不安を軽減できます。 - オプトイン・オプトアウトの選択肢を提示
利用者が明確にデータ提供の可否を選べるようにすると、「勝手に追跡された」という印象を与えにくくなります。 - 必要以上に細分化しすぎないターゲティング
ターゲットの明確化は広告効果を高めるうえで必須ですが、過剰になりすぎると気味悪さが先行します。適度な粒度での配信設計を心がけることが大切です。
プライバシー尊重の姿勢を示すことは、長期的にはブランドの信頼性を高める大きな要素となります。
ユーザーも安心して広告を受け取ることができ、企業に対して「しっかり配慮している」という好印象を抱きやすくなるでしょう。
過剰な煽りを避ける文言とクリエイティブ
- ポジティブかつ具体的なメリット訴求
ネガティブ表現よりも、「こんな良い未来が待っている」「これであなたの課題が解決する」という前向きなビジョンを描くことで、ユーザーに安心感を与えられます。 - 誇張しすぎない数字や効果説明
「たった1日で10倍痩せる!」のような非現実的な表現は、購買意欲より疑念を生みがちです。根拠のない誇大広告は規制対象にもなる恐れがあるため、注意が必要でしょう。 - ビジュアル面の清潔感と共感性
過激な色合いやショッキングなイメージより、商品やサービスがもたらす快適さや楽しさを連想させるクリエイティブのほうが、長期的に良い印象を残しやすいと考えられます。
「大きな結果をすぐに得たい」という想いから、不安を煽る広告に頼るのは短絡的といえます。
本当にユーザーの課題解決に寄り添う姿勢が伝わる表現を選ぶことが、ブランドイメージを守りつつ成果を上げる近道でしょう。
ポジティブな体験価値を重視した広告設計
- ユーザーの成功イメージを描くストーリー仕立て
サービス利用前と利用後の変化を、共感しやすい物語的な構成で描くと、ユーザーに自然な納得感を提供できます。 - 「安心・信頼」を訴求する要素の盛り込み
たとえば、実際のユーザーの声や口コミ、専門家のコメントなどを盛り込むと、うさんくささや気持ち悪さを感じにくくなります。 - インタラクティブ広告の活用
ユーザーが選択肢をクリックして進めるような参加型の広告は、受け手が広告を自発的に楽しめるため、不快感を抱きにくいメリットがあります。
ユーザーが広告を見て「嫌だな」ではなく、「面白い」「役に立ちそう」と感じる設計にシフトすることこそ、web広告が果たすべき理想的な役割と言えるでしょう。
単なる誘導ではなく、価値あるコミュニケーションの一環として捉えることが、長期的な顧客との関係を築く秘訣です。
ユーザー心理と広告クリエイティブの関係
前章で、不快感を与えないための設計ポイントを確認しましたが、さらに深掘りしてユーザー心理と広告クリエイティブの関係性を考えてみましょう。
広告クリエイティブは、画像や動画、テキストなど複数の要素で成り立っており、それぞれがユーザーの感情や行動に大きく作用します。
ここでは、心理学的アプローチやセグメントとのマッチング、そしてデザイン面の影響力について解説します。
企業側がユーザー視点を徹底的に意識したクリエイティブを作れるかどうかが、広告への不快感を大幅に減らすカギとなるでしょう。
不快な印象を避ける心理学的アプローチ
- 「単純接触効果」を正しく活用する
同じ広告を何度も見せると親近感が湧く「ザイオンス効果」と呼ばれる心理がありますが、回数や頻度が過度になれば嫌悪感へと変わる可能性もあります。ほどよい頻度管理が重要です。 - 色彩心理やフォント心理
暗い色や毒々しい配色、極端に崩れたフォントを多用すると、視覚的な不快感を抱く人が増えます。逆に淡い配色や整然としたフォントには安心感を感じる人が多いと言われています。 - 「損失回避バイアス」の悪用を避ける
人間は得をするより損をしないことを優先する傾向があります。これを過剰に利用して、「買わないと損をする!」ばかりを押し出すと、不安や拒絶感を煽りすぎる恐れがあります。
広告を制作する際は、こうした心理要素を理解したうえでポジティブに活用することが大切です。
無理に不安や恐怖を強調するより、安心感や親しみやすさを前面に出すほうが、長期的に好感度を高められる可能性が高いと言えます。
適切なターゲットセグメントと訴求メッセージの一致
- ユーザーの属性・興味関心との整合性
たとえば、若い世代に向けたファッション広告と、高齢者向けの介護サービス広告が混在するようなセグメントだと、誤配信による違和感が生じやすいです。 - メッセージの明確化
「〇〇な人へ向けたサービスです」というように、自分向けだと感じやすいコピーを用いれば、気持ち悪さよりも親近感を抱いてもらえる確率が高まります。 - 配信チャネルに合わせたクリエイティブ調整
SNSで表示する広告と、検索エンジンのテキスト広告では表現の適正が違います。それぞれに合った訴求メッセージを作り分ける工夫が重要です。
広告を見せる相手との距離感を適切に保つことが、不快感の軽減につながります。
ターゲティングが正確であっても、訴求内容がユーザーに合わなければ「押し売り感」が強まり、拒絶反応が生まれやすい点に注意が必要でしょう。
カラーデザインやフォントが与える潜在的影響
- ブランドカラーの統一感
広告と自社サイト、SNSアカウントなどで統一感を持たせることで、ユーザーが「一体感」や「プロフェッショナルさ」を感じやすくなります。バラバラなデザインを見せると雑多な印象となり、不快に感じる方もいます。 - アイキャッチ画像の心理的効果
視線誘導を考慮したレイアウトや、魅力的な人物・シーンを用いた画像は、「続きが見たい」という欲求を高めます。一方、無造作に配置された写真や不明瞭な画像は、安っぽさやチープな印象を与え、マイナスイメージにつながりかねません。 - フォントサイズや余白の取り方
文字が小さすぎたり、行間が詰まりすぎたりすると、読みにくさが不快感を増幅させます。特にスマートフォン表示では、余白の取り方ひとつで視認性が大きく変わり、広告の印象も左右されます。
ユーザーは広告を一瞬で判断するため、見た目の印象が全体的な評価に直結しやすいのです。
デザイン面での不快感をなくすだけでも、広告による「気持ち悪い」イメージを大幅に和らげることができます。
DXマーケティングが提供するWebマーケティングサービス
ここからは、具体的に「株式会社DXマーケティング」がどのようなサービスを提供し、企業のweb広告が『気持ち悪い』と思われない施策づくりを支援しているかをご紹介します。
当社は、単に広告運用を代行するだけでなく、ユーザー心理を重視したLP制作やLINE構築など、複数の施策を統合的にサポートしています。
特に、データ活用やクリエイティブ設計においては「不快感を生まない」ための配慮を重視しており、持続的に成果が出る施策を得意としているのが特徴です。
以下の3つの小見出しでは、それぞれのサービスの概要と、どのように不快感の少ない広告運用を実現できるのかを解説します。
WEBマーケティング全般をトータルで依頼できる強み
「株式会社DXマーケティング」では、戦略設計から広告運用、LP制作、さらにはLINE公式アカウントの構築までを一貫して依頼できます。
1つの施策だけ依頼しても成果が限定的になりやすいところを、全体最適を考えた上で運用できるのが強みです。
- ワンストップでのメリット
1:広告クリエイティブとLP、SNS施策などが連動しやすい
2:担当窓口が一元化され、コミュニケーションミスが減る
3:ブランドイメージやコンセプトを崩さずに施策を展開できる
不快感のある広告を避けながらも、ユーザー心理に寄り添う施策を作るには、さまざまなチャネルで一貫性を持たせる必要があります。
当社なら、包括的なアプローチで企業の魅力を伝えられるため、結果的に「広告が押し付けがましい」印象を与えにくくなるでしょう。
競合調査と心理的アプローチで成果を高めるLP制作
広告をクリックして初めてユーザーが目にするLPの印象は、ブランド全体のイメージを左右します。
「株式会社DXマーケティング」では、競合他社の分析や顧客心理の深掘りを行い、ユーザーが不快感や違和感を抱かないLP制作を行っています。
| 要素 | 内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 競合調査 | 同業他社のLPや広告手法をリサーチ | 差別化ポイントの明確化&市場ニーズの把握 |
| ユーザー心理を踏まえた構成 | 不安や煽りに頼らず、ポジティブな情報提供を重視 | 安心感と信頼感を与え、離脱を防ぐ |
| デザインとコピーの連動 | 読みやすく共感しやすい文章、見やすいレイアウト | 好印象を得やすく、コンバージョン率向上につながる |
例えば、ヘッドラインで「これをしないとダメ!」と脅すのではなく、「これがあれば、あなたの悩みをこう解決できます」と提案するアプローチを取るなど、不安を過度に煽らない構成を心がけています。
加えて、色彩やフォントにもこだわり、ユーザーが読み進めやすいLPを定期的にABテストし、最適化を続けているのが特長です。
LINE構築と広告運用の掛け合わせ効果
広告で興味を持ったユーザーを、どのように継続してファン化していくかという点では、LINE公式アカウントの活用が大きな武器となります。
「株式会社DXマーケティング」では、競合のLINE活用事例を分析しながら、顧客コミュニケーションを強化する設計を提案しています。
- LINE構築のポイント
1:クーポン配布や新商品情報を定期的に送信し、ユーザーとの接触頻度を高める
2:チャットボットを導入することで、24時間問い合わせ対応が可能に
3:アップセルやクロスセルの促進を、さりげないタイミングで実施し、不快感を与えない
LINE公式アカウントを活用すれば、企業の情報をタイムリーに届けるだけでなく、ユーザーとの温度感を保ちつつ販促を進められます。
こうした長期的なリレーションシップの構築は、短期的な煽り広告とは対極のアプローチとも言え、結果的に「気持ち悪い」と思われないマーケティングを実現する助けとなるでしょう。
まとめ
web広告が気持ち悪いと感じられる原因や、その回避策、さらにユーザーの心理を踏まえた広告設計のポイントについて、ここまで詳しく解説してきました。
不快な広告は、ユーザー体験を損ねるだけでなく、企業のイメージや売上にも大きな悪影響を及ぼします。
しかし、ユーザーに寄り添った設計と適切なコミュニケーションを心がければ、広告は「気持ち悪い」存在から「役立つ情報源」へと変化させられる可能性があります。
そのためには、企業側が単に煽りや過剰なターゲティングに頼らず、心理学を活用しながらポジティブな体験価値を提供できるかが大きな鍵となるでしょう。
もし、不快感のない広告運用やLP制作、さらに顧客との継続的な関係づくりについて専門家の力を借りたいと考えているなら、「株式会社DXマーケティング」がおすすめです。
当社では、以下のステップを通じて、安心かつ効果的なWEBマーケティング施策を提案いたします。
- 無料相談の申し込み
- 現状分析と提案
- カスタマイズされた見積もり
- 契約内容の確認と合意
- 契約とサービス開始
気軽にご相談いただける無料相談を行っていますので、まずはどんな施策が必要なのか、どのように改善していくべきかを一緒に考えてみませんか。
ユーザーに「気持ち悪い」と感じさせない広告こそが、長く愛されるブランドを育むための第一歩です。
ぜひお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
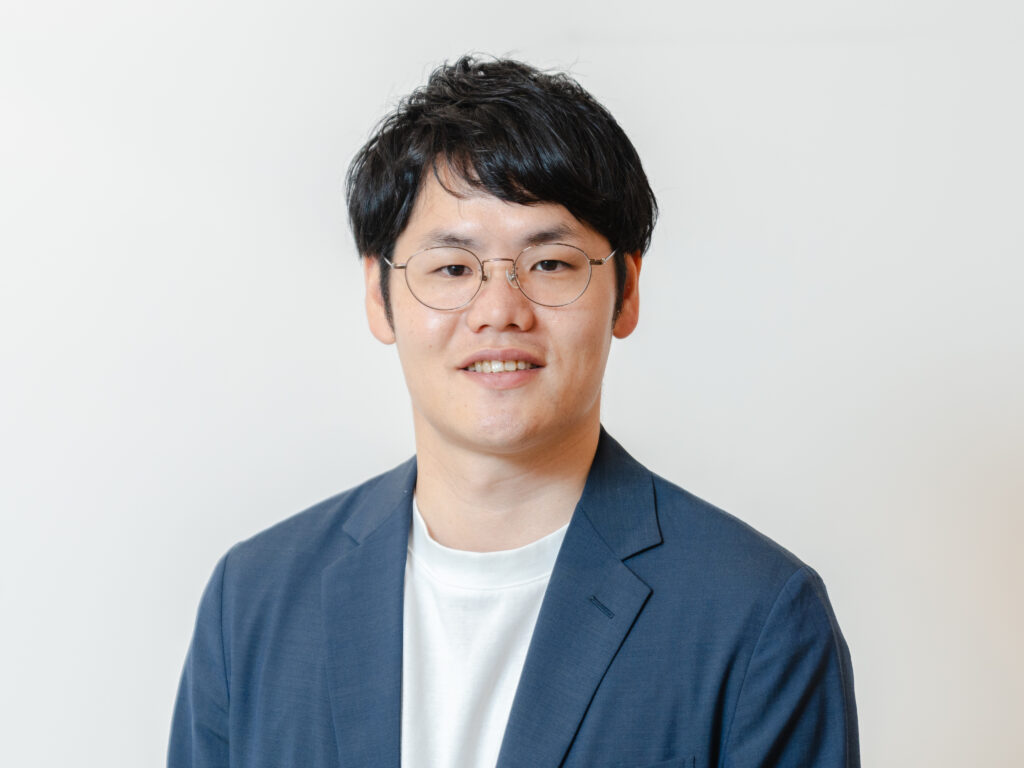
阿部 光平
Dx Marketing 代表
静岡県出身。東北大学大学院卒業後、大手インフラ企業で企画やマーケティングを担当。業績が評価され、部内で最も優秀な成績を収めた社員に贈られる「部長賞」を受賞する。独立後は、株式会社DX-マーケティングを設立し、大手企業で培った集客ノウハウを中小規模事業者さま/個人事業主さま向けに提供している。
\この記事をシェアする/
平日10時~17時


