- web広告の規制に不安を感じている方
- コンプライアンス体制をしっかり整えたい方
- 広告の表現方法に悩んでいる方
- マーケティング施策を包括的に見直したい方
こんにちは、「株式会社DXマーケティング」です。
近年、インターネット上での広告手法が多様化するなか、web広告の規制もますます厳しくなっていることをご存じでしょうか。
企業側が広告の表現や配信内容をしっかり管理しないと、景品表示法や薬機法などの法令に抵触するリスクが高まり、ブランドイメージの損失にもつながりかねません。
広告主としてはもちろん、代理店としても正しい知識と対策が求められる時代です。
ただ、一方で「具体的にどのような規制があるのか」「実際にどんな対策を取ればいいのか」と、情報が散在していて把握しづらい面もあるでしょう。
そこで本記事では、web広告の規制についての基礎知識や、規制をクリアしながら成果を伸ばすための施策を総合的に解説します。
あわせて、「株式会社DXマーケティング」が提供しているWEBマーケティング全般やLP制作、LINE構築、広告運用などのサービスをどう活用できるかにも触れながら、コンプライアンスと成果の両立をめざすヒントをお伝えします。
web広告における規制の基礎知識

オンライン上であっても、広告は法令を含む各種ガイドラインに従って運用しなくてはなりません。
テレビや雑誌などの従来メディアと比較すると、インターネットでは表現の自由度が高い分、思わぬところで規制を違反してしまう恐れがあります。
しかし裏を返せば、規制をしっかり理解して適切に広告を運用できれば、トラブル回避はもちろん信頼性の高いブランディングにもつなげることが可能です。
ここではまず、基礎的な視点を押さえておきましょう。
広告ガイドラインの重要性
広告主や代理店が意識すべき法律やガイドラインとしては、たとえば景品表示法や薬機法、特定商取引法、著作権関連などが挙げられます。
これらの法規制が設けられている背景には、消費者保護の観点や公正な取引を維持する狙いがあります。
- 景品表示法
主に商品の表示や広告の内容に対して「優良誤認」や「有利誤認」を防止するための法律。誤解を招く表現に敏感です。 - 薬機法
医薬品や健康食品などの効能効果を誇大に謳わないよう規制。web広告でも具体的根拠のない表現は違反対象となります。 - 著作権
他者が作成した画像や文章を無断で使用してはいけません。ネット上だからといって自由に転載する行為は厳しく取り締まられています。
特に誤解を与えるような誇大表現は、規制対象となりやすい部分です。
利用者を惑わせる表示や、根拠のない「No.1」表記、あるいは過度に高い効果を暗示する表現などは注意を要します。
当たり前のように感じられるかもしれませんが、複数の部署や担当者が広告制作に関わると、整合性が取れずに誤った文言が入るケースもあるため、ガイドラインを再度確認しておく価値は高いでしょう。
| 主な法令 | 規制対象 | 要注意表現 |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 誇大広告など | 「絶対」「必ず」など断定的訴求 |
| 薬機法 | 健康食品・医薬品 | 根拠のない効能効果の記載 |
| 著作権 | 画像・文章の無断使用 | 他サイトやSNS投稿のコピペ |
正しく運用される広告ほど、ユーザーは企業に対して安心感を抱きます。
規制だからといって単に「面倒な手続き」と捉えるのではなく、ブランド保護と社会的信用の確立に役立つポイントとして前向きに活かしたいところです。
規制対象となる表現とは
web広告で陥りがちな問題として、「宣伝したいがあまり、過度な言い回しを使ってしまう」というケースが挙げられます。
- 根拠を示せない数値やランキング
「当社の製品は〇〇業界で売上No.1!」といった主張は、第三者機関の証明がない限り危険です。 - 意図的に消費者を急かすフレーズ
「今すぐ買わないと損!」といった表現も、実際の価値提供を裏付ける要素がない場合は誤認を招きかねません。 - 医療効果を強調した文言
健康食品などで「治る」「改善する」という記載をするのは、薬機法に抵触する可能性が高く非常にリスクが大きいです。
消費者が広告を見た際に、合理的な根拠のない主張や誇張されたメリットだけが前面に立つと、規制当局からも指摘を受けやすくなります。
一度違反が指摘されると、広告掲載停止だけでなく、多大な社会的信用の損失にもつながるため注意が必要です。
違反リスクがもたらす影響
規制違反が発覚すると、単にその広告が取り下げられるだけでなく、企業イメージ全体を損ねる恐れがあります。
- 行政処分・罰金
悪質と判断されれば高額の罰金や業務停止などの処分を受ける可能性あり。 - 広告媒体からの掲載拒否
一度トラブルを起こした実績があると、主要な広告プラットフォームから「要注意広告主」として扱われるリスクがあります。 - 消費者の不信感
SNS等で拡散され、「あの企業は不当表示をしていた」と評判が広まりやすい時代です。
コンプライアンス違反が発生すると、その後の広告出稿にも大きく影響が生じかねません。
違反を避けるだけでなく、合法的でかつユーザーにとって分かりやすい情報提供を心がけることが、長期的には集客効果を高める近道といえるでしょう。
web広告規制が強化された背景
web広告にまつわる規制が強化されたのは、単に法律が厳しくなっただけが理由ではありません。
利用者の増加や社会のデジタル化に伴い、インターネット広告が大きな影響力を持つようになった結果、誇大表示や不適切な訴求が社会問題化するケースが増えています。
ここでは、背景を理解するために過去からの流れや最近のトラブル事例などを見ていきましょう。
法整備の歴史と社会的要因
インターネット広告が普及する以前から、広告に対する法規制は存在していました。
ただ、インターネット特有の速い拡散力と匿名性が、規制の抜け穴を大きくしてしまった面があります。
- 急速なSNS普及
一般ユーザーが情報発信を気軽に行える環境が整い、企業が拡散力を狙ったステルスマーケティングを活用するケースも増加。 - 誤情報の氾濫
フェイクニュースや根拠のない噂が大量に流布される中で、広告においても同様の誤解を招く表現が利用されやすくなった。 - 世界的なデジタル規制の流れ
欧州のGDPR(一般データ保護規則)など、個人情報保護を含むデジタル規制の厳格化が進むなか、日本でも法令を含めた対応が求められている。
こうした背景から、景品表示法や薬機法の適用範囲がweb広告へ広がり、法執行機関や消費者庁が積極的に取り締まるようになったのです。
SNS広告におけるトラブル事例
SNS広告は、ターゲットの細かい設定や拡散性の高さなど、マーケティング面では大きなメリットがあります。
しかし一方で、規制違反につながるリスクが大きいといわれています。
- 誇張したビフォーアフター
ダイエット商品の広告で過度な画像加工を施した結果、不当表示と判定される。 - ステルスマーケティング問題
広告であることを明示せずにインフルエンサーを起用し、後に「やらせ・サクラ」として世間から批判される。 - 個人情報の不正利用
SNSの利用データを勝手に広告配信に流用し、プライバシー侵害を指摘される。
ユーザーが日常的に利用するSNSだからこそ、消費者が抱く不信感や批判が拡散されやすい点も問題を大きくする要因です。
「株式会社DXマーケティング」の視点
「株式会社DXマーケティング」では、WEBマーケティング全般を包括的に行ううえで、常に最新の広告ガイドラインをチェックしながら施策を実施しています。
- 競合と比較した表現の調整
他社製品と比較する場合、客観的なエビデンスを明示し、誤解を与えない言い回しを用いる。 - 広告媒体ごとの規約確認
Google広告やMeta広告(Facebook広告)の審査基準を随時把握し、事前に不適切要素がないかをチェック。 - クライアントへのコンプライアンス指導
広告文面やLPの表示内容などを細かく精査し、法令やガイドラインに合致しているかを提案時点から検証。
サービス内容としてはLP制作やLINE構築、広告運用など幅広く手がけていますが、基本となるコンプライアンスを徹底することで、安心して長期的なマーケティング戦略を展開できるサポート体制を整えています。
| 主な強化背景 | 具体例 | 影響 |
|---|---|---|
| SNSの普及 | インフルエンサー広告、ステマ | 規制違反が拡散されやすい |
| 世界的規制強化 | GDPRなどのデータ保護 | 個人情報の扱いに厳格な基準 |
| 消費者意識の高まり | 誇大表現や偽レビューへの警戒 | 企業の信用低下が即拡散 |
広告の規制が強化される今こそ、正確な情報提供と法令遵守を実践する企業が評価されやすくなります。
そのためにも、web広告の専門家や代理店と連携しながら、適切な対策を講じることが不可欠といえるでしょう。
web広告規制を踏まえたクリエイティブ
規制を意識しながらも、ユーザーに魅力的に伝える方法はないのか。
ここが多くの広告主にとってのジレンマともいえます。
もちろん、ただおとなしく「当たり障りのない表現」に終始してしまうと、広告としての訴求力が薄れてしまうかもしれません。
大切なのは、法令やガイドラインを守ったうえで、いかにユーザーの興味を引き、正確な情報提供ができるかという点です。
正確かつ誤解を招かない表現
コンプライアンスを重視するうえで、最も重要なのは根拠の提示です。
- 数字・データの明示
例えば「顧客満足度90%」と訴求するなら、調査方法やサンプル数などを示して信憑性を高める。 - 第三者機関の評価
自社がNo.1を名乗るには、外部の客観的調査結果が必須。曖昧な「業界トップクラス」という表現よりも、エビデンスを示す方がユーザーの信頼は得やすい。 - 事実と意見の区別
「当社製品は多くのメディアで紹介されました」という文言を使う場合、実際に掲載された具体的な媒体名や記事URLを明確にする。
さらに、不必要な断定や絶対表現は避けることもポイントです。
「あなたの人生が必ず変わります!」といった主観的・強制的な語り口より、ユーザーが判断できる情報を誠実に提供する方が、結果的に「規制に抵触せず、かつコンバージョンも得られるクリエイティブ」につながります。
視覚要素と注意喚起
文字情報だけでなく、画像や動画もまた規制対象となります。
ダイエット系の広告で有名な「ビフォーアフター」写真などは、そのまま掲載すると景品表示法や薬機法に抵触する恐れがあります。
- 明確な根拠がない変化写真の使用
実際の利用者写真であっても、過度な加工や誇張があれば違反認定される可能性が高い。 - 小さく表記される注意書き
「個人差があります」と書いてあっても、主たるメッセージと矛盾するような表現だと逆効果になりうる。 - ビジュアル表現とコピーの整合性
たとえば健康食品の広告で「すぐに痩せる」といった文字と、筋肉隆々の体型を強調した写真を組み合わせると、誤解を誘導したとみなされるかもしれません。
こうしたリスクを回避するには、広告のコンセプト設計の段階で法務や代理店、デザイナーと密に連携し、適切な範囲でユーザーを惹きつけられる表現を議論しておくことが必要です。
「株式会社DXマーケティング」のサービスで対応
「株式会社DXマーケティング」が行うLP制作や広告運用のサポートでは、クリエイティブ制作時点から規制をクリアするためのアドバイスを組み込みます。
- 競合他社の広告・LP調査
他社がどのような表現を使っているかを分析し、規制違反の余地や逆に差別化できるポイントを洗い出す。 - 文章・デザインの整合性チェック
誇張や誤解が生じる要因を排除しながら、商品やサービスの魅力を最大限に伝えるためのコピーライティングを提案。 - 定期的なABテスト
規制を守るだけではなく、複数案を試しながら効果測定を行う。法令違反リスクゼロ化と成果の両立を追求。
下記の通り、広告クリエイティブに求められる要素を整理し、クライアント企業ごとに最適化するのが大きな特長です。
| チェック項目 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 表現の正確性 | 法令遵守と誤解防止 | 「調査結果」「第三者認証」の提示 |
| 画像・動画の選定 | 過度な加工防止、実態を反映 | ビフォーアフターの利用可否 |
| 注意書きの見やすさ | 隠れたリスク回避 | 小さな文字で埋没しない位置に配置 |
コンプライアンスを守りながら魅力的な広告を作りたいという企業は、ぜひ専門家の意見を取り入れてみてください。
web広告規制と効果的なマーケティング連携
規制を意識すると、どうしても「表現を抑制する」方向に思考が偏りがちです。
しかし、マーケティングの視点で考えれば、規制に縛られた状態でも成果を追求する方法はいくらでもあります。
要は、ターゲットや媒体の特性をしっかり理解し、法令に抵触しない範囲で最適な施策を打つことが肝要です。
運用型広告における法令遵守
Google広告やSNS広告などの運用型広告は、日々のデータに基づいて入札金額や配信ターゲットを調整し、費用対効果を高める仕組みです。
- キーワード選定時の注意
「怪しい効果」を想起させる文言を設定すると、広告審査で落ちたり、配信停止の恐れがあります。 - 広告審査システムへの適応
GoogleやFacebookなどは自動審査と人力審査を組み合わせているため、違反要素があれば即ブロックされるケースも。 - 表現のテストと最適化
複数の広告パターンを作成し、コンプライアンスを満たす形でクリック率やコンバージョン率を見極める。
最初から大がかりな制作を行うよりも、小規模テストを繰り返しながら規制と成果のバランスを探るのが効率的です。
LINE構築で顧客との信頼を深める
広告運用だけでなく、ユーザーとの長期的な接点づくりも重要です。
そこで注目されるのが、LINE構築による顧客コミュニケーションの強化。
- 友だち追加後のクーポン配布
目的をはき違えた過度な勧誘はNGですが、適切なキャンペーン運用を行うことで規制をクリアしつつ購買意欲を高められる。 - チャットボットでの情報提供
利用規約や特定商取引法に基づく情報をチャットボットで提示するなど、自動応答で丁寧な対応が可能。 - プライバシーポリシーの明示
友だち追加時に、個人情報の取り扱いをユーザーがしっかり把握できる仕組みを整備しておく。
メッセージアプリはユーザーとの距離が近いぶん、一歩間違えると「迷惑行為」に発展しかねません。
しかし正しく運用すれば、規制を侵さない形で継続的にブランドへの好感度を高めるチャネルとして機能します。
広告とLP制作の一貫性
運用型広告やSNS広告でユーザーを集めても、最終的に商品購入や問い合わせにつながらなければ成果とは言えません。
ここで重要なのが、広告の訴求内容とLP(ランディングページ)の整合性です。
- 同じ表現ルール
広告で「〇〇が無料!」と謳っているのに、LPでは「条件付き有料」と表示していると不当表示とみなされる可能性がある。 - スムーズな訴求フロー
広告のコピーとLPの内容が噛み合っていないと、ユーザーが混乱し離脱率が高まる。 - サイト全体の法令表示
LPにおける特定商取引法表示やプライバシーポリシーなど、必要情報を見やすくまとめることで規制リスクを避ける。
「株式会社DXマーケティング」では、広告運用とLP制作を切り離さずに一貫してサポート。
規制を考慮した表現でユーザーを集客しつつ、LP上でも適切に情報を伝えてコンバージョンにつなげる体制を整えています。
| 連携ポイント | 具体的対策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 広告運用 | 運用型広告の審査基準を遵守 | 予算とコンプライアンスの最適化 |
| LINE構築 | 友だち追加やクーポン配布の適正化 | 継続的な顧客ロイヤルティ向上 |
| LP制作 | 広告コピーと矛盾しない表示内容 | 離脱率軽減、成約率アップ |
規制に強いクリエイティブとユーザーに寄り添うマーケティング施策を同時に実施することで、大きな成果を得るチャンスが広がるはずです。
規制を順守しながら成果を高める方法
コンプライアンスをしっかり意識しつつ、どうやってweb広告の成果を伸ばすか。
ここでは、より実践的なアプローチとして、データ分析や内部体制の構築方法などを取り上げます。
データ分析とターゲット最適化
web広告は運用型が中心となっており、クリックやコンバージョンといった具体的なデータをリアルタイムで追える利点があります。
- 広告グループ単位の管理
キーワードやオーディエンスごとに違反リスクや成果を分析し、効率の悪い配信を早期に見直す。 - クエリとCVデータの紐付け
どの検索クエリ経由でコンバージョンが発生したのか、ユーザーの意図と広告表現のマッチ度をチェック。 - リターゲティング戦略
一度サイトを訪れたが離脱したユーザーに適切なアプローチを行い、再来訪・成約を狙う。
データを活用すれば、違法性のある表現を避けつつ、最も費用対効果の高い層に対して広告を最適化できます。
コンプライアンスの見直しと教育
企業としてweb広告を継続的に運用するのであれば、社内外でのコンプライアンス教育も欠かせません。
- 法務担当や外部専門家との連携
重要なキャンペーンや新商品プロモーションの際は、事前に広告表現をチェックしてもらう。 - ガイドラインの定期更新
社内マニュアルや制作ルールをアップデートし、業界動向や法改正に合わせて随時見直す。 - 担当者研修
デザイナーやライター、運用担当など、それぞれが基本的な規制ポイントを理解しているかを定期的に確認。
特に大きな問題が起きてから対策するのでは遅いため、日常業務の中にコンプライアンス意識を根付かせることが大切です。
「株式会社DXマーケティング」の統合サポート
「株式会社DXマーケティング」では、広告運用をはじめとしたWEBマーケティング全般において、法令やガイドラインを踏まえた施策提案を行っています。
- ワンストップ対応
広告運用、LP制作、LINE構築などを一括して依頼できるため、社内で複数ベンダーを管理する手間が省け、コンプライアンス統制もしやすい。 - 競合調査と表現の最適化
市場の動向を調べつつ違反リスクを回避するコピーやデザインを作成。複数案のテストで成果を検証。 - 運用データのレポーティング
リアルタイムで広告成果を把握しながら、規制違反リスクが生じない範囲でアグレッシブに最適化を進める。
下表のように、企業が包括的なサポートを受けるメリットは大きいと言えるでしょう。
| サポート領域 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| WEBマーケティング全般 | 戦略設計から運用・改善提案 | 施策ごとの連携がスムーズ |
| LP制作 | 競合分析・デザイン・コピーライティング | 表現規制と訴求力を両立 |
| LINE構築 | 友だち獲得からクーポン配信・チャットボット運用 | 顧客との長期的関係強化 |
| 広告運用 | Google広告・Meta広告などの運用最適化 | 法遵守しつつ短期成果も狙える |
規制を守りながら利益を拡大していくには、専門知識と実践ノウハウが必要です。
自社だけで対応しきれない部分は、ぜひプロの助けを借りてみてください。
まとめ
web広告の規制は今後さらに強化されていくことが予想される中、企業側としてはコンプライアンスを守りつつ成果も落とさない運用体制が求められています。
しかし、規制に縛られて表現を過度に抑え込んでしまうと、魅力ある訴求ができずに広告効果が下がる危険性もあります。
そこで大切なのは、法令遵守とユーザーニーズを両立するための柔軟な戦略を持つことです。
web広告が合う・合わないという単純な問題ではなく、どのようにコンテンツを作り、どのように運用を継続的に改善していくかによって大きな差が生まれます。
もし、広告表現や運用体制についてお悩みであれば、「株式会社DXマーケティング」のサービスをご検討ください。
以下のステップでご相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
- 無料相談の申し込み
- 現状分析と提案
- カスタマイズされた見積もり
- 契約内容の確認と合意
- 契約とサービス開始
WEBマーケティング全般を含めた包括的な施策提案を行いながら、コンプライアンス対策や広告運用、LP制作、LINE構築などをワンストップでサポートいたします。
web広告を有効活用し、健全かつ確実にビジネスを成長させるために、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。
この記事を書いた人
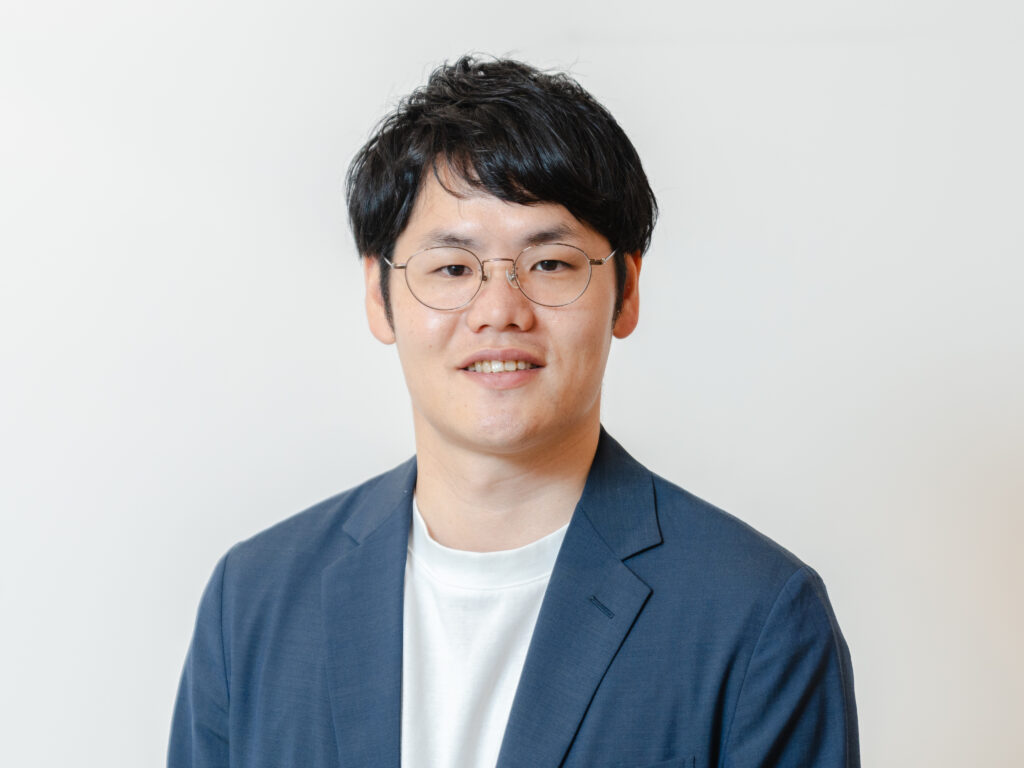
阿部 光平
Dx Marketing 代表
静岡県出身。東北大学大学院卒業後、大手インフラ企業で企画やマーケティングを担当。業績が評価され、部内で最も優秀な成績を収めた社員に贈られる「部長賞」を受賞する。独立後は、株式会社DX-マーケティングを設立し、大手企業で培った集客ノウハウを中小規模事業者さま/個人事業主さま向けに提供している。
\この記事をシェアする/
平日10時~17時


